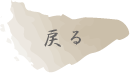造形インタラクティブティブとアフォーダンス
素体アートの制作を進める中で、私は最終的に造形インタラクティブという概念にたどり着いた。現代的なインタラクティブテクノロジーテクノロジーを用いないで、主に造形的な力を用いることでインタラクティブ・コミュニケーションを実現するインタラクティブな芸術を、私は造形インタラクティブという概念に集約したのだ。
そして、造形インタラクティブを作品として具現化するための方法論として、過去に追及したインタラクティブの理論と実践に加えて、日本文化のコミュニケーションの伝統や見立ての文化を大いに参考にした。それに加えて、重要な概念として近年浮上した考えがアフォーダンスである。
アフォーダンスとはジェームズ・ギブソン(米の知覚心理学者)によって1960年代に完成された生体心理学の認知理論であり、人間の認知の方法の解明に一石を投じた。
「マクドナルドでハンバーガーを買え」などという人間が自明にこなしている簡単な情報処理でさえロボットに行わせるのは困難であるが、ロボットにすべての知識を事前に与えなければ人間に似た行動をさせることができないというフレーム問題のジレンマにも、アフォーダンスは一定の理解の道筋を開いた。
従来の認知理論では、経験や学習によって得た情報処理のメカニズムによって認知が成立しているというノイマン型コンピュータに似た考えが主流だったが、実際の認知においてはそうしたデジタル的な発想の理論では解明できない認知の事実が存在した。
ギブソンは認知には単に演繹的に外部情報を情報処理するだけではなくて、人間や動物が環境の中に実在して直接的に知覚するものがあることに注目した。
アフォーダンスという語は、「与える/もたらす」の動詞affordを名詞化したギブソンの造語で、環境の一部である人間や動物が自然の中から環境が本来提供している価値ある情報を直接的にピックアップしていると考えたのである。
例えば、人に襲いかかるトラに出くわして人間はすぐさま危険を回避しようと判断するが、それは知識によって与えられたものではない。イスは知識として知っているものが椅子ではなく、座ることをアフォードしているのがイスの本質であり、だから山の岩にイスを発見できるし、程よい高さの欄干は本来の目的とは別にイスとして機能してしまう。
こうしたアフォーダンスの概念はインタラクティブアートの理論に重要な切り口を与える。人間を自然なコミュニケーションを成立させるためには、無意識に訴えて実際の行動を促すような力が必要とされるが、自然の中にはアフォーダンスが満ちており、人工的なデザインであっても有用な概念であることをアフォーダンスは明解に示したのである。
アフォーダンスという認知の視点から見ると、日本文化のコミュニケーションの特徴や見立ての文化は、アフォーダンスの本質を無意識的に理解して応用し洗練させてきた日本文化の姿を見ることができる。
また、分析の結果を総合して全体を理解するというデジタル的な発想の理解パターンとは異なり、最初からアプリオリに自己に与えたものとして全体性を認知して実際の行動を発動させるような認知があることの神秘をアフォーダンスは開示した。
物理世界の理解でも似たようなことが現代物理学に存在する。量子論は物質の本質が粒子的な性質と同時に波動的な性質を有することを明らかにした。
粒子はひとつふたつと数えることができるデジタル的性質である一方、波動は状態を示す数えることができないアナログ的な性質である。粒子と波動という性質は哲学や認識論的には両立しない概念であるにもかかわらず、この相反する性質の両方を具有するのが物質の本質であると量子論は教えるのである。
科学は分析と総合という西洋的な発想のアプローチを得意としてきた。しかしそこには全体を全体として受け入れる発想が欠けていた。部分の集合が全体を必ずしも開示するのではなく、全体を全体として理解する方法論の重要性が認識されていなかったといえる。
日本的な感性や発想には、常に自然という環境を人間とつながるものとしての理解があり、自然や八百万の神々との調和を図ろうとする行動原理が生まれてきた。そしてそれが日本的なコミュニケーションを育んできたと言えるだろう。
見えないものの向こうにものを見るという行為はすべての芸術の根本に繋がる。絵画は実在する世界の忠実な投影であるという幻想があるが、物理的には絵の具が乗ったキャンバスでしかないのである。それでも芸術が存在するのは、芸術という物理的な存在があるからではない。そこには人間主体の存在を前提とした芸術的なコミュニケーションが必ずや存在するのであり、芸術の内容の本質とは分析な理解や考察だけでは到達できないものが必ず含まれている。
アフォードするものを理解できる人間存在が存在しなければ、そもそも芸術というコミュニケーション自体が存在しないだろうし、複雑なインタラクティブなコミュニケーションの成立などありえない現象であろう。そうした意味では、すべての芸術は広い意味でのインタラクティブアートであるといっても過言ではないだろう。
造形インタラクティブという企ては、そのような人間の認知の本質や芸術というコミュニケーションが成立する意味を意識しつつ、造形を通して鑑賞者に主体的コミュニケーションを成立させることを目標とする芸術であろうとするインタラクティブアートへのひとつの挑戦だといえる。
そして、素体アートにおいて私は造形インタラクティブを意識した造形を試行錯誤し、その最初の成果を個展で紹介するに到った。