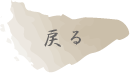日本文化にみるインタラクティブティブ文化
素体アートの模索の中で私はインタラクティブアートを常に意識してきた。一見したところ、私が過去に制作してきた作品群とは明らかな違いがあるように見えるが、制作意図には一貫した繋がりが存在する。
一般に知られているインタラクティブアートとはテクノロジーを利用して自律的な動作をしたり、外部情報を処理することによって反応を生み出す仕組み有するものが主流である。しかし、このような物理的特徴だけを捉えてインタラクティブというのであれば、本質の理解を踏み外することになるだろう。そうした機械系主体の工学的な情報処理メカニズムは、インタラクティブではなくサイバネティックと呼ばれるもののである。
インタラクティブとは機械系が反応することではなく、人間が主体となってコミュニケ―ションする様態のことであり、その点がサイバネティックとは大きく異なるのである。
インタラクティブなコミュニケーションを成立させるためにサイバネティックな構造を利用することは有効な手段である。しかし、サイバネティックなシステムそのものが目指すものはあくまでも応用に照らした機械系としての完成度であり、人間はその外部情報を成すにすぎない。
一方インタラクティブなシステムとはあくまでも人間を主体とした情報系であり、反応するは機械ではなく人間であり、人間主体の中に創性を喚起する可能性を常に内包するものである。
20数年来私は、インタラクティブアートの作品とは究極には人間の中に作られるものであると主張して続けてきた。しかし、世の中に浸透したインタラクティブアートのイメージとは、情報系テクノロジーの芸術への応用事例、誰かが必ず考えだすであろうアイデアのデモンストレーション、アミューズメント的なガジェットなど、外見的な目新しさや楽しさばかりが目立ち、芸術のコミュニケーションの本質に真剣に迫ろうとする試みが非常に少ないという残念な状況が続いている。
インタラクティブなシステムを構築するための正攻法のひとつは、センシング技術や情報処理によって外部情報に反応するシステムを利用することであろう。私も先端のテクノロジーに常に注目し、テクノロジーを有効に利用することで新たな芸術コミュニケーションの可能性を自己の表現で追及してきた。しかし、そうしたテクノロジーに頼った方法論でないもうひとつの正攻法が存在すると私は信じるようになった。
茶の湯や日本庭園、日本建築、日本画などの日本の伝統芸術の中に、インタラクティブアートのもうひとつの可能性の大きなヒントが隠されている。
茶の湯は日本芸術のひとつだが、茶室や茶道具をはじめ作法などのさまざまな要素が絡み合うものであるが、それぞれの総合が芸術の本質ではなく、茶の湯の本質はもてなしであり、それによって生み出される体験そのものである。
また、日本庭園の踏み石は単なる歩くための足場ではなく、自然な足幅に合わせた配置がされ、何の説明がなくても踏み石を歩くよう人はナビゲーションされる。そして、その時人の視線は足もとに集中させられ、それを抜けた瞬間に移された視線は次に開ける空間に誘われるというような仕組みが施されている。
このような仕掛けはあたかもインタラクティブなコンテンツのコンピュータ・プログラムのようである。ゲームやバーチャルリアリティのサイバースペースで人間をナビゲートするプログラムと同様な高度な機能が、日本文化の伝統の中に脈々と息づいてきたのである。